黙っていること、ひとりになること~ヴァージニア・ウルフさんの『燈台へ』
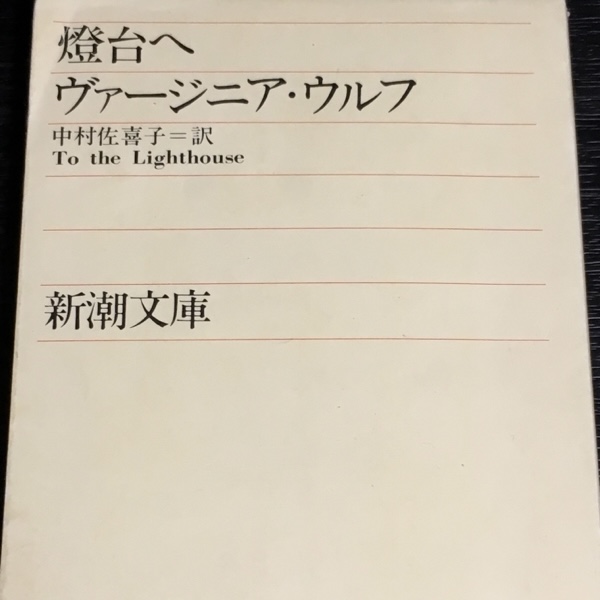
ヴァージニア・ウルフさんの『燈台へ』。
ずっと昔、高校生の頃に手にいれたのですが、読んだのか読んでいないのかも忘れてしまっている本でした。
借りて読んでいたレベッカ・ソルニットさんの『説教をしたがる男たち』の本に、ヴァージニア・ウルフさんのことが書いてあったので再び手にとりました。
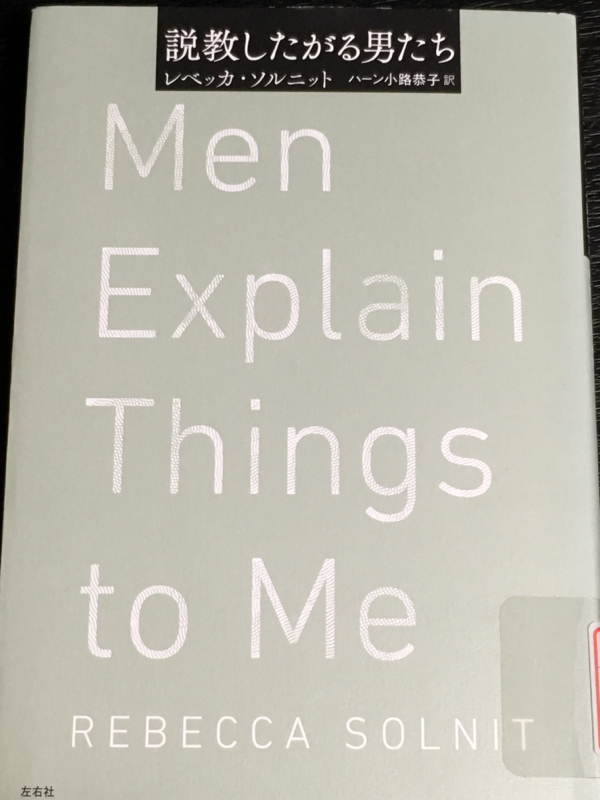
『燈台へ」で、ウルフは書いている。
いまはもう、だれのことも考えなくていい。自分自身で、ひとりきりでいられる。近頃はそうしなくてはならないと思うことがよくあった。考えるために ―いえ、考えるためですらない。黙っているため、ひとりになるために。あらゆる存在や行為、拡がりをもち、きらめき、声を発しているものは蒸発してしまった。そのとき人はある種の荘厳さをもって自分自身になり、楔形の闇の中心へ、ほかの人たちには見えないなにかへと収縮していく。背筋をのばして腰かけ、編み物を続ける間にも、心の中ではそんな風に感じていた。そしてくっついているものをすべて取り払ってしまうと、自己はどんな不思議な冒険でも自由に受け入れることができる。生命が少しの間動きを止めると、経験できることの範囲は果てしなく思える。(中略)その下には闇が四方に拡がっていて、底知れない深さだった。でもときどき私たちは表面へと浮かび上がってくる。それが、他人から見た自分というものだ。地平線は果てしなく拡がっているように思えた。
[レベッカ・ソルニット、『説教をしたがる男たち』より]
『燈台へ』の主人公は、ひとりでいる時間がなく、ひとりになって自分に戻れる時間の大切さをしみじみ感じています。
同じくだりは、新潮文庫の『燈台へ』(中村佐喜子さん訳)ではこう訳されています。
もう誰にも気がねは要らない。自分だけだ、自分だけが相手だ。そして近ごろよく、その必要を感じるのだけれど、―考えること、いや、あえて考えなくといゝ。黙っていること、ひとりになることである。実在と行為、拡がり、輝き、声、そういうものがみんな消滅してしまう、そして人は、荘厳な感覚のうちに、ひとには見えぬ真黒の、くさび型をした精髄である自我へ縮小してゆく。夫人は編ものをつゞけながら姿勢よく坐っているけれど、自分がそんなものになってゆく感じであった。
そして、贅物を取りのぞかれたこの自我は、自由にふしぎな冒険ができそうに思われた。一と時、実生活がなくなると、経験の範囲は無限になってゆく。
[ヴァージニア・ウルフ、『燈台へ』(新潮文庫、中村佐喜子=訳)より]
岩波文庫(御輿哲也/訳)の『灯台へ』での訳です。少し前の文章から引用します。
そうだわ、と夫人は、ジェイムズが切り抜いた冷蔵庫、芝刈機、礼服姿の紳士の絵などを片づけながら、しみじみ思った―子どもは決して忘れない。だからこそ、大人が何を言い何をするかはとても重要で、あの子たちが寝てしまうと、どこかホッとする。これでやっと誰に対しても気を遣わなくてすむ。一人になって、わたし自身に戻れる。そしてそれは、最近しばしば彼女がその必要を感じることだった――考えること、いや考えることでさえなく、ただ黙って一人になること。すると日頃の自分のあり方や行動、きらきら輝き、響き合いながら広がっていたすべてのものが、ゆっくり姿を消していく。やがて厳かな感じとともに、自分が本来の自分に帰っていくような、他人には見えない楔形をした暗闇の芯になるような、そんな気がする。相変わらずすわって編物を続けながら、夫人はこんなふうに自分の存在を感じていた。そしてこの隠れた自分は、余分なもの一切を脱ぎ捨てているので、自由に未知の冒険に乗り出すこともできそうだった。
[ヴァージニア・ウルフ、『灯台へ』(岩波文庫、御輿哲也=訳)より]
この「黙っていること、ひとりになること」について、ヴァージニア・ウルフさんや、メイ・サートンさん、アン・モロウ・リンドバーグさんが自身の著作に書いています。
引用多めですが転記します。
メイ・サートンさんの『独り居の日記』では、「自分だけの時間」としてこう書かかれています。
家事や家族の雑用をこえて、彼らがしたいことを行なうための空間をつくり出すことは、女にとっての方がよほどむずかしい。女の生活はこまぎれである……私がたいへんな数の手紙から受けとるのは、その嘆きである ーー 『自分だけの部屋』〔ヴァージニア・ウルフの著名の題名〕というよりも自分だけの時間を求めての叫びなのだ。どんな事柄についてであれ、少なくともその解決を試みるためのゆとりがない日は、深刻な問題になる。
[メイ・サートン、『独り居の日記』より]
食事の支度、洗濯、掃除、育児、買い物などを毎日こなしている女性(女性だけとは限らないですが)について、メイ・サートンさんの「女の生活はこまぎれである」というくだりに納得できます。
アン・モロウ・リンドバーグさんの『海からの贈物』の一節にも、「一人で静かに時間を過す」ことの大切さが書かれています。
女はそれとは反対に、一人で静かに時間を過すとか、ゆっくりものを考えるとか、お祈りとか、音楽とか、その他、読書でも、勉強でも、仕事でも、自分の内部に向わせて、今日の世界に働いている各種の遠心力な力に抵抗するものを求めなければならない。それは体を使ってすることでも、知的なことでも、芸術的なことでも、自分に創造的な生き方をさせるものなら何でも構わないのである。それは大規模な仕事や計画でなくてもいいが、自分でやるものでなくてはならなくて、朝、花瓶一つに花を活けるのは、詩を一つ書いたり、一度だけでもお祈りするのと同様に、忙しい一日の間、或る静かな気持を失わずにいる結果になることもある。要するに、少しでも自分の内部に注意を向ける時間があることが大切でなのである。
[リンドバーグ夫人、『海からの贈物』より]
我々は今日、一人になることを恐れるあま余りに、決して一人になることがなくなっている。家族や、友達や、映画の助けが借りられない時でも、ラジオやテレビがあって、寂しいというのが悩みの種だった女も、今日ではもう一人にされる心配はない。家で仕事をしている時でも、流行歌手が脇にいて歌ってくれる。昔の女のように一人で空想に耽るほうが、まだしもこれよりは独創的なものを持っていた。それは少なくとも、自分でやらなければならないことで、そしてそれは自分の内的な生活を豊かにした。しかし今日では、私たちは私たちの孤独の世界に自分の夢を咲かせる代りに、そこを絶え間ない音楽やお喋りで埋めて、そして我々はそれを聞いてさえもいない。
[リンドバーグ夫人、『海からの贈物』より]
『燈台』の初版は1927年、『海からの贈物』の初版は1955年。
自身の「時間」について明確に意識しどうあればいいのかを考えていますが、これは現代でも同じような状況ではないでしょうか。。
ヴァージニア・ウルフさんの『自分だけの部屋』は持っているはずなのですがどうしても見つからないので、もう1度買おうかなと思っています。
これら紹介した本は、将来新刊を仕入れることがあればお店にも置ければなって思っています。
一人でいることについては、串田孫一さんの『山のパンセ』、アーノルド・ローベルさんの『ふたりはきょうも』にも書かれています。また時間をみて紹介したいと思います。









コメント